���
���
���s�̌��t
����Q�o�߂̗R��
�w���t�W�x���l�~�Ɍ�����(�~�u���g�m�J�l�}�T)�̂�߂�
�W�H�� �ʂ��璹�̖����� ����Q�o�߂ʐ{���̊֎炪����B
�̈ӂ́u�ޕ��ɕ����ԒW�H�����玄��l��F�Ǝv���Ă���邩�̂悤�ɐ璹���ʂ��Ă���B
�{���̊֎�̎��͊��邱�����ČǓƂ̊�����J�����܂ܒ����}���邱�Ƃ��낤�B�v
�Q�Ɓu�~�ӏ܂̎O�@�v
�����ł͔~�̊ӏ܂ɂ�
���炫�̔~����ֈ�֒T���Ȃ���y���ނ��Ƃ��u�T�~�v�A
�炫��������~���y���ނ��Ƃ��u�ܔ~�v�A
�U��䂭�~��ɂ��݂Ȃ��爤�ł邱�Ƃ��u���~�v�Ƃ��������ł��B
���������Ӗ��ł́A���傱���ł�����Ȕ~�Ƃ������ƂɂȂ�B
����ÖɂȂ�قǑ����炭�悤�ɂȂ�B
�P�O���̖����܂��t�̎c�邤�����Q���c���ł��āA���t�ƂƂ��ɏ����ȉԂ��炩���钿�����i�� (�ɑ��炫)������B
�~�̉ԂƖ𖡂키�i�ӏ܂̎d���jNHK�@���̚₩�甲��
��̚��@�F�@�炫�͂��߂Ɍ����날��
���͖��J���ӏ܂��邪�A�~�͈Ⴄ�B
���̂Ȃ��ɂ��͋������߂��炫�͂��߂̉ԁA���ꂱ�����A�~�̐^�����Ȃ̂ł��B
��̚��@�F�@�}�Ԃ肪���V���̔�
��������̊G�t�E���i���́u�l�G�Ԓ��}���v�̏t�̏�ʂ̎�l���͔~�̘V�ł��B
�����ւ̓����~�ɑ����Ă����Ƃ������Ƃ���Ȃ��ł����ˁB
�O�̚��@�F�@�����Ĉ��ł�F�͗l
�������A�������ƂɁA���ƐԂ����݂ɍ炢�āA���؋��̂悤�ɂ��낢��ς���Ă����B
���������Ƃ��낪�����Ă݂Ă̊y���݂���Ȃ��ł��傤���B
�����Ԃ������Ȃ��ŐԂ�����Ɖ₢���C�����ɂȂ�Ǝv���܂��B����������ƁA�V�������
��������������āA��J���y����������l���̐F�͗l�𖡂킦��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�~�̉ԐF
 �{�g�i�ق�ׂɁj
�{�g�i�ق�ׂɁj
�Ԃт�ɂ�̂��閾�邢�g�F�̂���
 �ڔ��i���肵��j
�ڔ��i���肵��j
�ڂ݂̂����̓s���N�F�����Ă��邪�A�J�Ԃ���Ɣ��ɕς�����
 �ڍg�i����ׂɁj
�ڍg�i����ׂɁj
�ڂ݂̂����͔����F�����Ă��邪�A�J�Ԃ���ƍg�F�ɂȂ����
 ���g�i�����ׂɁj
���g�i�����ׂɁj
�ԕق̎��ӂ�����肵���悤�ɍg���Ȃ��Ă���A�c�̕������W���F�ɂȂ����
�@�@
TOP �~���j���[ �擪����
�}�ς��
�}�ς��i���������j�Ƃ́A�A���̂���}�����Ɋւ��āA�V��E�t�E�ԁE�ʎ��Ȃǂ��A�����_�̓ˑR�ψقȂǂɂ���āA���̌̂������Ă����`�`���Ƃ͈Ⴄ���̂��錻�ۂł���B
��h(�������キ)�̗R��
���̔~�Ɖ��̌��т��́u���t�W�v�̎��ォ��ł��邪�A�w��������x�̎���ɂ́A�~�̖��a�̏h�Ƃ������z�����܂�A��ł��Ă����B
�w��������x��肨�悻�����I�O�̕������㒆���̓V��N�� (947-957�j�ɐ����a�̔~���͂ꂽ�̂ŁA
�����Ō@���点�����A�悭����Ǝ}�ɕ������ѕt�����Ă���
�̉̂��t�����Ă����B
����������ɂȂ�ꂽ�V�c�́A����Ǝv��������Č��̎�ɕԂ��ꂽ�Ƃ�����B
�̂̎�͋I�єV (�L�m�c�����L)�̖��ʼn̖̂��l�Ƃ���ꂽ
�����肱�̔~�́A���h�~�Ƃ��ėL���ɂȂ����B
�܂��A���̌̎��ɂ��₩���āA��ɂ��̗����u���h�̗W (����)�v�Ƃ����悤�ɂȂ����ƌ����Ă���B
���̖��������̒�ɏ��肽���ƍl�����l�B���A��{�~�̎}����ږؗp����̂��đ�� �ڂ��A�ɐB�����Ă������B
�a�h�~�͗��j�Ɏc�閼�Ƃ��čg���̍炫�����ł��������A
��̍̂���ɂ���Ċ֓��n���ɂ͑щ����F�̉Ԃ����܂�A
���n���ɂ͍g�F���ɐB���邱�ƂɂȂ�A���ꂪ�L�܂����B
���~(�I�E�o�C)
���N�Z�C�ȂłU�ق̉��F�̉Ԃ����邪���͂Ȃ��B
 TOP
�~���j���[
�擪����
TOP
�~���j���[
�擪�����}�i���肦���j�̃G�s�\�[�h
��h�̖��̗R���ƂȂ�u���Ȃ���Ƃ����������@��̏h�͂Ɩ��Δ@�������ށv�̉̂́A�V�c�ɓ͂���ꂽ�̎}�Ɍ��т���ꂽ���ɏ�����Ă��܂����B
���̃G�s�\�[�h���悭�m���Ă����������� �w��������x�ɂ��̔��z�����܂����B
�������̕��̂����A�܂�����𑗂鎞�ɂ́A�} (�I���G�_)�Ƃ����āA�������Ԃ̖̎}�ȂǂɌ��ѕt���܂��B
�����Ȑ����i�ǂ������N���� �O���j�̉Ԗ��p����ꂽ���A���������A���̉Ԃɐ�삯�č炭�~�́A��̂ق��D��ŗp�����A��ꂽ�}�ł��B
���s�̌��t
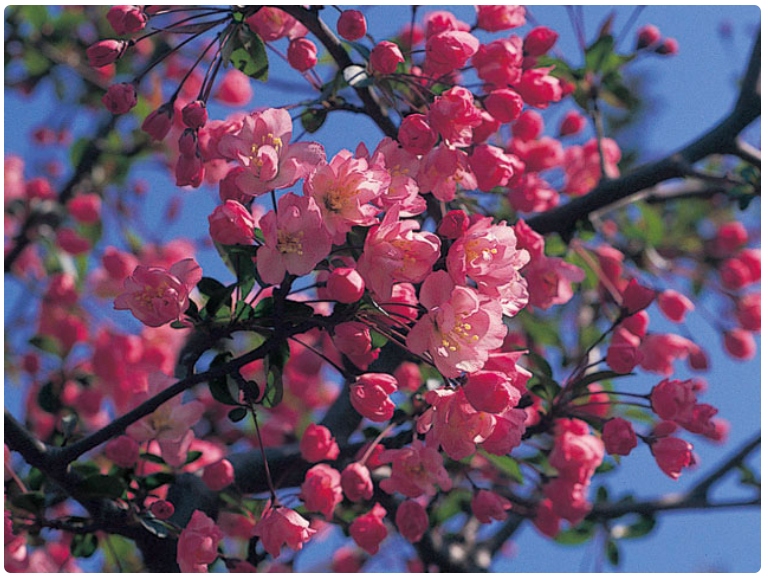 �@�@
�@�@�y�f�W�^���厫��z���
�@�@
�P�D �o���Ȃ̗��t�����B�}�͎��F�Ő��ꉺ����A�t�͑ȉ~�`�B
4������A�g�F�̉Ԃ��������ɍ炫�A���͊ۂ��A�����F�ɏn���B
�����̌��Y�ŁA��Ȃǂɂ���B
���}(������)�C���B��(�͂�)�C���B
�s�G �t�t�u�C���┒���ɍg������܂Ă�^�����v
�@�@
�Q �D�~�J�C�h�E�̌Ö��B
TOP �~���j���[ �擪����
���ꁁ�ΐ쌧�H
�u������v�� �u����v�́A���Đ_�ސ쌧�ɂ��������������ꑺ�Ƃ����n��������ꂽ���̂ŁA�ΐ쌧�̉���Ƃ͉��̊W���Ȃ��B
���ɔ~���ɓK���Ă���Ƃ���A�~���Ȃǂɉ��H����E���̑�\�I�ȕi��B
�ʎ���25g���x�ŁA�ʔ�̐F�͒W���ΐF�����Ă���A�O���A�i���Ƃ��ɗD��Ă���B
"���납�� �ƌĂ�ł��镶���������B
�Ԏ�(������)
�Ԃ̂����ׂƂ߂��ׂ̂��Ă����B��(����)�B�ԐS(������)�B

TOP �~���j���[ �擪����
�ؔ_�ʒ��̖��O�̗R��
�{���w�ؔZ�ʒ�=�ؔZ�����x�Ƃ����i�햼�������ŁA
���ӂ��炷��A�u�ؔZ�v�́u�ʔX�v���������悤�����A�D�������āu�ؔZ�v�ƕ\�����ꂽ�ƍl������B
�O���̉ԕق͔��d�ł���Ƃ��납��A�u�ʒ��v�̖����t����ꂽ�ƌ����Ă���B
�u�Z�v�̌��ӂ́A�u�Z���v�ȊO�ɂ��u�Z�₩���������v�Ƃ����Ӗ�������A�]���āu�ؔZ�v�Ƃ����p���͌�p�������ł���B
�u�ʒ��v���������́A�����̒��ł��鎩�ʂ̎����́u�ʒ��v�̂��Ƃł����āA�ԕق̔�����\�L���Ė��t�����Ă���B
�{���̈Ӗ���m��Ȃ���l�B���A�P�ɓlj��݂̂ŁA�u���v�̎��Ăėp�������̂ƍl������B
�܂�����ɂ��A�����ł͉͉ԁA�_�͉ʎ��A�ؔ_�͉Ԏ����p��̈Ӗ��ł���B
�ʒ��͔��Ԕ��d�̈Ӗ��ł���A����Ɓu�Ԏ����p���d���Ԏ�v�ƂȂ�B
�Ȃ��A��t�̉Ԃ͓��{�ł͂܂��������B
���فi���ׂ�j�Ƃ�
���`��(���傤������)�ŁA����ɂ���1���̉Ԃт�B���𗧂Ă��悤�Ȍ`�Ȃ̂ł����B
 TOP
�~���j���[
�擪����
TOP
�~���j���[
�擪����������
�o���Ȃ̎��ɍ炭�Ԃœ����P�{�̖̒��ɍg����2�F��3�F�̉Ԃ��炩������̂������Ă��܂�
�����̐킢�̊��ԂƔ��������̂ł��̂悤�ɍ炭�Ԃ�Ⴆ�ČĂ悤�ł��B
�悭��������̂ɂ͉ԓ����L��܂����؉Z��~�ɂ������炪�����܂��B
���l�̈Ӗ��Ɏg���錾�t�Ƃ��ẮA�ֈႢ�i������j�A �炫�����Ȃǂ�����B
�Q�l �u�]�쏊���v�̂����
�����O������̐l�A���M (�肭����)���A�]�삩�璷���̐e�F���@ (�͂�悤)�ɑ��炫�̔~�̉Ԃ���}����A
�̂��ɒ����ɍs���Ă��̗F�ɑ��������Ɂu�]�얳���L�A�ցi��傤�j����}�t�v�Ƃ����Ƃ����B
�u�����䊰�v�Ɉ����u�t�B�L�v�̌̎�����u�]��͑��蕨�������Ȃ����ł�����}�̍���܂��v�Ƃ���A
(��}�̏t)�͔~�ٖ̈��ƂȂ����B
�������A�����ɂ͏����s�݂Ƃ������p�傪����A�������͖������鏊�ɂ���Ƃ������Ӗ��ł���B
���̔~�� "�]�쏊���s��"�̗��ł͂Ȃ����Ƃ̐�������B
�Q�l �u�ցv�i��傤�j
���ǂ� �����E
�P�ǂ� �������i���j�A����i��j�A���́i���ށj
�Ӗ� ������B���肪����B�����B���̂ށB�����ɂ���B�y���ށB���������B�����B������ƁB���肻�߁B���炭
�Q�l�u�����̌ꌹ�E�R���v
�����͌Ñ㒆���́u���v�̍�����`�������D����ɂ���č��ꂽ�D�����������B
�������A�P�Ɂu���̕��v�̈Ӗ�����u�����v�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B
�Â��A�����́u����͂Ƃ�v�Ƃ������B
�u����͂Ƃ�v�́u���D�v�Ƃ�������A�u����v�́u���v�̍����Ӗ����A�u�͂Ƃ�v�́u�͂�����(�@�D��)�v�̕ω�������ł���B
(�u�����v���u�͂��Ƃ�v�Ɠǂނ��Ƃ��A�u�͂�����v�Ɠǂނ��Ƃ��u�͂�����v�ɗR������B)
���́u����(����͂Ƃ�)�v�����ǂ��ꂽ�ꂪ�u���ӂ��v�ł���B���̂��߁A�����́u��(����)�v�������̂ł͂Ȃ��A�u�D��(����)�v�������̂ł���B
��⽁i�����Ă�j �����u⽁v
��⽂̈Ӗ��͍��F���痧����锒���ŁA���x�u��⽁v�̍炢�Ă���l����⽂̗l�����疼�t����ꂽ�B
�~�̕i�햼�ɂȂ�O���獁⽂Ƃ������t�͑��݂����B
�w�势�a���T�x�w���ʁx�w�����厖�T�x�ɂ��f�ڂ���Ă���B
�~�̕i�햼�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���̈Ӗ�������B
��L�̂ق��ɐF�X�ȏ���������B
�@�u⽁i�Ă�j�v�ɂ́A⽏��̎��̂̂悤�Ɏ}���N�j���N�j���Ȃ��Ă���ƌ����Ӗ������߂��Ă��āA
�u���v�ɂ́A�Ԃ̗ǂ�����Ƃ����Ӗ����������Ă���B
�A �}�Ԃ���_���ĂѓV�ɏ�间�̗l�Ɍ����Ăĕʖ��_���~
�B���������������O�A�č��킩�A�����ɂ�������ɍ����l�߂ČO�ׂ�����⽂Ƃ����B
���̍��݂Ƃ̗ގ�����⽂̖��ɂȂ�B
�C�����͏㏸����Ɠ���B���̕������l���獁⽂̖��ƂȂ�B
�D���j�̓y�U����ɉ_���^������B���̘r�̂��������Ɠ����}�U��ʼn_���~�̖��ƂȂ�B
���X�B���̐��̂��̂Ǝv���Ȃ����͋C�̎}�U��B
�Q�l �u���~�v�̖��O�ւ̎���
�]�ˎ���ɂ����~�Ə����Ă���B
�u���v�͏����̂ق��A�ւ�(����)�A�����߂���(����)�K�v�Ƃ���A�̈Ӗ������邪�A����ł͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��B
"��"�Ɏ���"��i���j"���Ə������A���ɑ���Ȃ��i�T�W�j�A�}�f�Ȃǂ̈Ӗ�������A
��~ (���h�Ȕ~�łȂ��~)�����~�̂Ȃ����̂ł�?
���s�̌��t
�炭�₱�̉ԁE�E�E
�u��g�Â� �炭�₱�̉� �~������ �����t�ׂ� �炭�₱�̉ԁv�@���m(���)
���Z���邽�ɂ����āA��ԍŏ��ɓǂ܂��a�̂��Ƃ̂��ƁB
�S�l���ɓ����Ă���a�̂ł͂���܂��A�r�܂��悤�Ɍ��܂��Ă���炵���ł��B
�y���_�~�z������
�E���̕ώ�B�Ԃ͔��d�̔��F�܂��͒W�g�F�Ŏ����ׂ�������B
��̉ԂɂS�`�V�̉ʎ������Ԃ��́B
�Ϗܗp�ɍ͔|�����B
�����n���Ȃ������ɂP�Â����čs���̂����_�ɗႦ�Ă��̖�������B
����߁A�݂����B
�y���_�z�����
��b�R�V��@���őm�����ԍ��ɂȂ��ċ��`�ɂ��đ��_����B
�������҂͎ԍ����狎���čs���B�Ō�̎c�����҂������B
�Q�Ɓu���_�̕i�햼�̗R���v
�~�̕i�햼�ȗ��́A�閾���O�Ɉ��F�ɂ��܂��̂悤�ȉԂт�̗l����̈ӁB
�@ ���_�Ƃ͓��{�̌Ì�ňł�����ւƈڍs����閾���O�Ɉ��F�ɂ��܂����Ӗ�����B
�Í��a�̏W�Ɂu���_�̂ق���ق���Ɩ����䂯�E�E�E�v�Ƃ���B
�A �������ɁA���̋�ɂ��Ȃт��_�B
�w�ꌹ�R�����T�x�ɂ��A�����Łu���_�v�Ə����̂́A���̋�̈Ӗ�����̓��Ď��B
�ꌹ�́u�̖ځv�ł��낤�B�Ñ�̉��ǂłفA������̖�ڂ����Ă����e���Ԗڂ̕������u�ځv�Ƃ����A
�|���ޗ��Ƃ��Ďg���Ă������߁u�̖ځv�ƌĂꂽ�B
���́u�̖ځv���u������v���̂��̂��Ӗ�����悤�ɂȂ�A�]���āu�閾���̔�������v��u�閾���v���u���̂̂߁v�Ƃ����悤�ɂȂ����B
�w�L�����x�ɂ����L�̂悤�ɁA���l�̉�����Ȃ���Ă���B
(����ɂ����B�u�߁v�͌��n�I�Z���̖�����̖�ڂ��ʂ����Ă����ԑ�l�̑e���҂ݖڂ̂��ƂŁA�|���ޗ��Ƃ��đ���ꂽ�u�߁v���u�̖ځv�ƌĂꂽ�B
���ꂪ�A�����肻�̂��̂̈ӂɂȂ�A�]���Ė閾���̔�������A�X�ɖ閾�����̂��̂̈ӂɂȂ���)
���������A�������A�����ڂ́B
�햼�i����߂��j
�����̎��\�����O�̂��ƁB
������i���������ځj
������͂Q�l����B
�@���̃E�C�O���n����т��x�z�����������A
�V�r�̔ȂɏZ�܂������B�ՖʗL���ł������ƋL����Ă���B
�v���Ɋ�̓��n���ՖʂƂȂ�A�Ղ̖��̈�ۂ����������Ɣ��W�����̂ł��낤�B
�A�Ђ���āi�R�������j�R���ɏZ�܂�����受�B
�Ƃ��Ɏ��̍c���U�����ݐ��N�̉Y�����Y��������B
�d���Ƒf�X�ƁA�~�̐�����͂ǂ���̖�����������̂ł��낤�B
�u���������ځv�Ƃ������B
���J�Ƃ�
�A�i���ׁj�̌`���A�Ԃ̐c�i�Ԃ̒��S�B�����ׂƂ߂��ׁB�Ԏ�(������)�j�𒆐S�ɋK���������L�����Ă������
�p���i���������j
�p���Ƃ́F���̂悤�ɏW�܂��Đ����邱�ƁB�u�������v�Ɠ��`�B
���s�̌��t
����
�A���̐����ŁA�s��}���������Đ������鐫��
�ƂƂ�
���� �Ɓi�ӂ���� �� ���߂����j�́A���q���㒆���̌��ƁE�̐l�B
�����k�ƌ�q�����A����ʁE�����[��������Ƃ̎O�j�B���ʂ͐���ʁE����[���B
�u��⤁v�Ƃ͂ǂ��������̂Ȃ̂ł��傤���H
�܂��͓ǂݕ��B�u��⤁v�Ə����āu���Ⴙ��v�Ɠǂ݂܂��B
�����ł́A�����q�̒��ɓ��ꂽ�������Ƃ��������������킹��̂ł����A���̍s�ׂ��u������_�Ă�v�ƌ����A���̂�����_�Ă�Ƃ��ɗp����̂��u��⤁v�B
�܂蒃⤂Ƃ����̂́A�����ł�������_�Ă�Ƃ��Ɏg�p���铹��̈��Ȃ̂ł��B
 �����̓_�ĕ��������̊e���h�ɂ���ĈႢ�A�������ƖA���Ă�ꍇ�A�����łȂ��ꍇ�Ƃ���܂��B
�����̓_�ĕ��������̊e���h�ɂ���ĈႢ�A�������ƖA���Ă�ꍇ�A�����łȂ��ꍇ�Ƃ���܂��B
�u��⤁v�́A��������A���Ă铹��Ǝv������������ł����A�����܂ł��A������������������ƍ��킹�邽�߂̓���ł��B
TOP �~���j���[ �擪����
�Ă�����̗R��
�u�Ă�����~�v�̕i�햼�̗R���́A�J�ԂƓ����ɉԕق������A���F���A�i���ׁj�������c��Ƃ��납�炫�Ă���B
���F���A���A�e�ԂɎ��Ă���̂ʼn����Ñ�̐��b�u
�{���A�u�e�~�v�Ɩ����������������A���ɑ��̔~�ɂƂ��Ă���B
�܂��A���~�R��ł���B
������A�����P���ɃL�N�E���Ƃ����u�Ă�����~�v�Ƃ��ĈႢ�Ñ�ɑz����y�����̂��B
���̗R���ɂ͑傫�ȃ��}���Ɨ��j������B
�ڍׂ͏ȗ����邪�A�w�����L�x�ɖ}�����̂悤�Ȑ��b���L����Ă���B
�w�����L�x�̐��b
���̖s���́A�悢�n����ɓ�����X�����A�ߑ��ɏo��������߂����������܂����B
���ꂪ�A�@�،o���̒���
��i���A�T���X�N���b�g��j�Ƃ́A���T�̂Ȃ��ŁA���̋����╧�E��F�̓�����������̂ɉC���̌`���ŏq�ׂ����́B
���鎞�A�邪�����Ȃ����Ă������q���A�߂��Ē�̌䖍���܂����ł��܂��܂����B
�����āA�ނ͖�b�̏Z�ނ悤�Ȏ₵���e�b�P���ɗ��߂ɂ���܂��B
�����m������́A���킢�����Ɏv���A��̔��{�̘�̂����̓��������Ɠ`���Ȃ���܂����B
�����ꂽ�����͔߂��݂Ȃ������Ɍ��˂ꂽ�ʂ�ɁA������ꂽ��������Ă��܂������A
������������Y��Ă��܂����Ƃ����邩������Ȃ��Ǝv���A�e�̗t�ɂ���������t���܂����B
���̌�A���̋e�̗t�ɂ��܂����I���킸���������āA��𗬂�鐅�����ׂēV�̊ØI�̗��ɂȂ����̂ł��B
�������A�̊��������ڂ��Ă��̐������ނƑ�ϊÂ��A�ǂ�Ȓ����ɂ������Ă��܂����B
�����āA�V�l���Ԃ�����Ĕ��A�S��������낦�ĕ�d���܂����̂ŁA��b�̐S�z���Ȃ��Ȃ�܂����B
����ǂ��납�A���}�Ȏ����ɉH��������l�ƂȂ����̂ł��B
���ꂾ���łȂ��A�J�̉����̐�������ł����O�S�]���̐l�X�́A�F�a�C������s�V�s���̒�����ۂ��̂ł����B
�������āA����͈ڂ蔪�S�]�N�̂̂��܂ŁA�����͏��N�̗e�e�ŁA�V�������邱�Ƃ�����܂���ł����B
���������A鰂̕���̂Ƃ��A�����͏���������d�c�i�ق����j�Ɩ���ς������ɁA���̘��ɂ��������܂����B
�y�����L���\�O �u���n�i�t�̎��v���z
�\�y�u�e�����v�ł́A�����o�Ă��܂����A�������d�c�ɕς�����Ƃ����Ă��܂���B
���̂悤�ɏ������A�����W����Ă��܂��B
�܂��A���̖����Ɂu�e�̘I�v�� �u�e�{�v�����邪�A���̌̎����疽�����ꂽ�B
�ԉ��i�Ă����j�Ƃ�
�ԉ��ɂ͑щ��A�Ή��ȂǕʂ̌Ăѕ�������܂��B
���Ƃ��ƐA���̌s���ɂ��鐶���_�ɓˑR�ψق��N����A�����ɐL�т���A�я�ɐ�������O���I�ȕό`���݂��錻�ۂ�̂̂��Ƃł��B
�s�⍪�A�ʎ���ԂȂǂɂ��N���錻�ۂł��B
�P�C�g�E�̉Ԃ����͂��Ƃ��ƒԉ��ł����A��`�I�ɂ��̕ψق����`�����c�������̂ł��B
������ł͂����ς�s�⊲�ŋN���A���̓Ɠ��Ȍ`���������p���y���݂܂��B
�ψقɂ����̂Ȃ̂ŁA���ʂ̌̂ɔ�ׂĒ��������߉��l�������Ȃ�A����Ɍ̍����傫���Ȃ�܂��B
���蒆�Ƃ�
����i�ǂ��Ă��A�p: identify, identification�j�Ƃ́A�Ȋw�S�ʂ̗p��ŁA����Ώۂɂ��Ă��ꂪ�u���ł��邩�v��˂��~�߂�s�ׁi���O�E���́E���ꐫ����肷��s�ׁj���w���B
�@�@
���肷��A�����ƂƂ��\�L�����B�ދ`��͔��B����ɂ���ėl�X�Ȏg����������B
�@�@
�����w�i���ފw�j�ɂ����ē���ƌ����A�햼�ׂ�s�ׂ��w���B
�u�ˏo�v�̑�~�̕i��R��
�u�ˏo�v�̑�~�̕i��R���́A��̉H�т������ւ��A�Y��ɂȂ�˂���o���Ƃ��̂悤�ɂ��ꂢ�Ȕ~�ԁB
�P�D���������肵�Ă����邪�H�т������ւ�Ē�������ł邱�ƁB
*�S��(�ق����ЂႭ����j-�� �u�Ƃ�ł̑�̂��ӎ����v
�Q�D�������Ⓓ���������яo�邱�ƁB
�R�D�~�ł��킸������V���������ĕa�����o�邱�ƁB
*���i�������q�H�j�E�X��d����b��Z�u���͂��ɂ���|�́A�Ƃ�o�̉ʂƂ��Ă��āv
�ȍs�̌��t
�썂�~�̗R��
�a�̎R�������S�암(�~�i�x)�쑺�ӈ��
���a26�N�A��암�_���ƒn���̓암���Z���@�|�������Y�������ő����̗D�njn���I�莖�Ƃ��s�������ʁA
���̗D�G�Ȍn���̂�������I�ꂽ�V�n���̒��ōł��������̗ǂ��n���ł���B
���a4O�N�Ɏ�c���̂��o�^���ꂽ�i��ł���B
�암�쑺��
�ŋ߂ł͌�҂݂̂��m���Ă���B
�I�B�ł́u�i���R�E�o�C�v�Ƃ��u�i���R�E�E���v�Ƃ������Ă���ō����i��̎��~�B
�с@�� �ɂ������傤
�~�ɂ͋ѐ�(�j�V�L�V���E)�ƌ����āA�}�ɉ��F�┒�̔�(�t)�̓�����̂�����B
�����A�ؓ��肪�V���ɍׂ������邾���Ȃ̂ɁA�V���S���A�܂��ّ啔���̗������ĉ��F��悷����̂�"�ѐ�"�ƌĂ�ł���B
���̉��F�����ɍg�F�������邱�Ƃ�����̂Łu��F���сv�Ƃ����̂����m��Ȃ��B
��������̂ŋѐD��̋т����m��Ȃ��B
�~�ɓ��ɂ₯�ĐF�X�ɕϐF���āA����Y��Ȏ}�ɂȂ鐫���������Ă���B
���̕i��͋ѐ��̏o�钇�Ԃł͎����������炿���ǂ��ق��ł���B
"����"�͍炫���������Ă��邪�A���̂ǂ�����ɂ���ďo���ɍ�������
����
�u�����v�Ղ́A�����E���a�N�ԁi1800�N�O��j���A�L���˂̔ˈ�ł���㓡�����i���傤�݂�j�������̏��c�S�V�����ɊJ�����A����4�N�i1871�j�ɔp���ɂȂ����ˉc�̖��Ղł��B
���{�l�͎}����D��
���{�l�͎}������D��ň琬�ۑ������B
���Ȃ�̕i�킪���ʂ̕i��̕ώ�Ƃ��Ĕ������ꂽ�B
�u�����v����u�����}���ˁv�A
�u���e�v����u���e�}���ˁv�A
�Ȃǂŗ��҂̉Ԃ̌`�͎��Ă���B
�������A�u�v�w�~�}���ˁv�Ȃǂ͓Ǝ��ɂ���ꂽ�B
�͍s�̌��t
�S�̂Ƃ�
100��̘a�̂��W�߂����́B��l��100��r�ނ��́A��l1���100��W�߂����̂Ȃǂ�����B�S��̉́B�S��a�́B
�w�S��x�͈Ƃ̌���Ƃ��āA���̗��h�ɑ��܂ꂽ���̂ł���B
�L��~�n���̗���
�{��́u��`�v�A�P�P(1957)����ɁA�L��~�̖��̂́u���쎞��ɖL��̉P�n��傪�Q�Ό��̍ہA���̎������Q�����B
��ɂ��ꂪ�������L��̍��ɎY����Ƃ����Ӗ��ŖL��~�Ɩ��t����ꂽ�v�Əq�ׁA�^�U�̂ڂǂ͕s���ł���Ƃ��q�ׂĂ���B
�L��ŕ��Ⴊ�������̂��A"����"�Ƃ��������B
���� "�L��"�ƌĂ��ɁA���d�A���ԂȂǒ������ώ킪����A�i��ł͂Ȃ��ނ���i��Q�ł���B
�����ɂ��n���Ă���A�F�̔Z�W�ɂ��"�L��B"�W�L��"�ɕ������Ă���B
�܍s�̌��t
���~�i�݂��߁j�Ƃ��Ă� �u�a�h�v
���~�Ƃ��Ă� �u�a�h�v�ْW�g�F�̈�d�̑�֎�B�ʎ��͑傫���A�U�����{�`���{�ɏn���B
�����͗ǂ����A�������ʂ��N�ɂ�葽����������̂����_�B
�z�E�f���R�Ő����Ղ��B�Ԕ~�́u�a�h�v�Ƃ͈قȂ�i��ŁA�������ŌÂ�����͔|����Ă����v�i��B
�������_�R���̔_�Ƃ��吳�����ɘa�̎R�����瓱����������琶�����i��Ƃ�����B
�����͂�⋭���A�������ł���B
�}�̔����͂�▧�ŁA�Z�ʎ}��������������B
�}�̐F�͑��̕i��ɔ�חΐF���Z���B
�ԉ�̋x�������͔�r�I�����̂ŁA�J�Ԋ������܂邱�Ƃ�����B
�������ō͔|�B
���m�ӂ̌����`��
�u���m�Ӂ����W�v�ɂ́A�́A�t�̖�V�тŒm�荇��������̎Ⴂ�j�������݂��ɍD�ӂ����������A
�������ƂɗV�тɗ���悤�ɒj����U�������A
�j���͋M���̉Ƃ̏��݂�����Ȃ��̂� �u�ǂ�������ǂ��̂ł��傤���v�Ɛq�˂�ƁA
���́u���ň�Ԕ������~�̉Ԃ��炢�Ă���Ƃ�ڎw���Ă�������₢�v�Ɖ������B
�j�͌���ꂽ�Ƃ���ɖ��̉Ƃ�{�����Ă��Ƃ����X�g�[���[���[�N���ꂽ�����`��������B
������̕i����ǂ̋�S
���̍����͓ˑR�ψقłقȂ��A���ǂ��d�˂č�������̂ł���B
�����A�~�͐V���i���傤�j��ڂ���Ɏg�����A����͉��̕�����̕����t�̊Ԋu���l��A�t�̌`���傫���Ȃ�B
�]���āA�Ԃ���ւɂȂ�B
����ɒ��ڂ������̂ł����ĐV���̐�[������̂��ČJ��Ԃ��ڂ��ŁA��ւ̉Ԃ����̂ɕ��S�����B
�������A��͔~�����D���ȓ���p�����B
������ɐڂ��A�V���̐�[���Ăї��N������ɐڂ����Ƃ��P�W�N�J��Ԃ����B
���߂ĉԂ��炩�����Ƃ���A�P�W�N�O�̌���̉Ԃɔ�ׂāA�ԕقP���ŕ��ʉԈ�ւ̑傫�����������Ƃ����B
�i����ǂ͂���������S��ς�l���������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
������̖��̗R��
���̗R��:"������"�ٌ��݂̓����s�ƍ�ʌ��ɍL����^�ϑ�n�������A
������͍L��ŁA��ڂ� "������s�����Ȃ�"�Ƃ��납��u���݂����Ȃ��v�ɂ����āA�傫�Ȕu�������B
����́u���̔��i�����̂����j�v�ɂłĂ���B
��s�̌��t
�ށi�₭�j
�ށi�₭�j�́A�����ׂ̐�[�ɂ���A�ԕ����ޑ�̊튯�B�}���Q��
��s�̌��t
�ֈႢ�i������j
�o���Ȃ̎��ɍ炭�Ԃœ����P�{�̖̒��ɍg����2�F��3�F�̉Ԃ��炩������̂ʂ́w�������x�ƌ����Ă��܂�
�����̐킢�̊��ԂƔ��������̂ł��̂悤�ɍ炭�Ԃ�Ⴆ�ČĂ悤�ł��B
�悭��������̂ɂ͉ԓ����L��܂����؉Z��~�ɂ������炪�����܂��`
�Ҏq�~�́u�Ҏq�v�Ƃ�
�u�T�r�V�C�q�g�v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A
�u�ҁv�ɂ́u�T�r�V�C�v�Ƃ����Ӗ��ȊO�Ɂu�V�^�^���v�Ƃ����Ӗ�������A
�J�Ԓ��O���Q�̐F�ƌ`���A���ɏh�荡�ɂ��H�藎�������ȘI�̓H�Ɍ����ĂĖ��t�����Ă���B
�u�J���v�i�낤����j�̈Ӗ����l�@
�������Ђ��Ƃ��Ď��`����l�@���Ă݂�ƁA�u�J�v�ɂ́u�J��(�l�M���E)�v�A
�u���v�ɂ́u�ւ肭����=�T����v�̈Ӗ�������A�����Q���q����Ɓu�ւ肭�����Ă˂��炤�v�ƂȂ��āA
����ł͂������肵�����߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
��������ݍ���ōl�@���Ă݂�ƁA�u���v�̌��ӂ́A���t���T����Ƃ������ƂŁA
�ڏ�̐l���Ȑl�ɂ́A�`��Ȍ��t���T���Č������Ȃ���A���ꂾ���ň�w�Z�i���܁j�₩�ȗD�����S�������K�v�ɂȂ�B
���̂��Ƃ� �u�J�v�فu�ւ肭����v�̈Ӗ��ɂ��ꂽ�o�܂Ǝv����B
���̂��Ƃ���u�J���v�̈Ӗ��́A�u���̂͌���ʂ����Ă��邾���ŐS�̒ꂩ��J(�l�M��)���Ă����ԁv
�u�S�Z�₩�ɂ��ėD�����J��v�ƂȂ�A�����Ƃ��ɂ��̉Ԃɂӂ��킵�����������i�햼�ƂȂ�B
��s�̌��t
�����i�킢���j�Ƃ�
���A�����߉��̐����̈�ʓI�ȑ傫���������`�Ȃ܂ܐ��n���邱�Ƃ��w���B��ɉ��|����ɂ����Ďg����p��B
�@�@
����Ȋ���(�ꗗ)
�� ���� �A ���� � �Ă� ���� ���i��傤�j
����Ȋ���
�� ����


�A ����


� ��


����


���i��傤�j
���ǂ� �����E
�P�ǂ� �������i���j�A����i��j�A���́i���ށj
�Ӗ� ������B���肪����B�����B���̂ށB�����ɂ���B�y���ށB���������B�����B������ƁB���肻�߁B���炭�B
